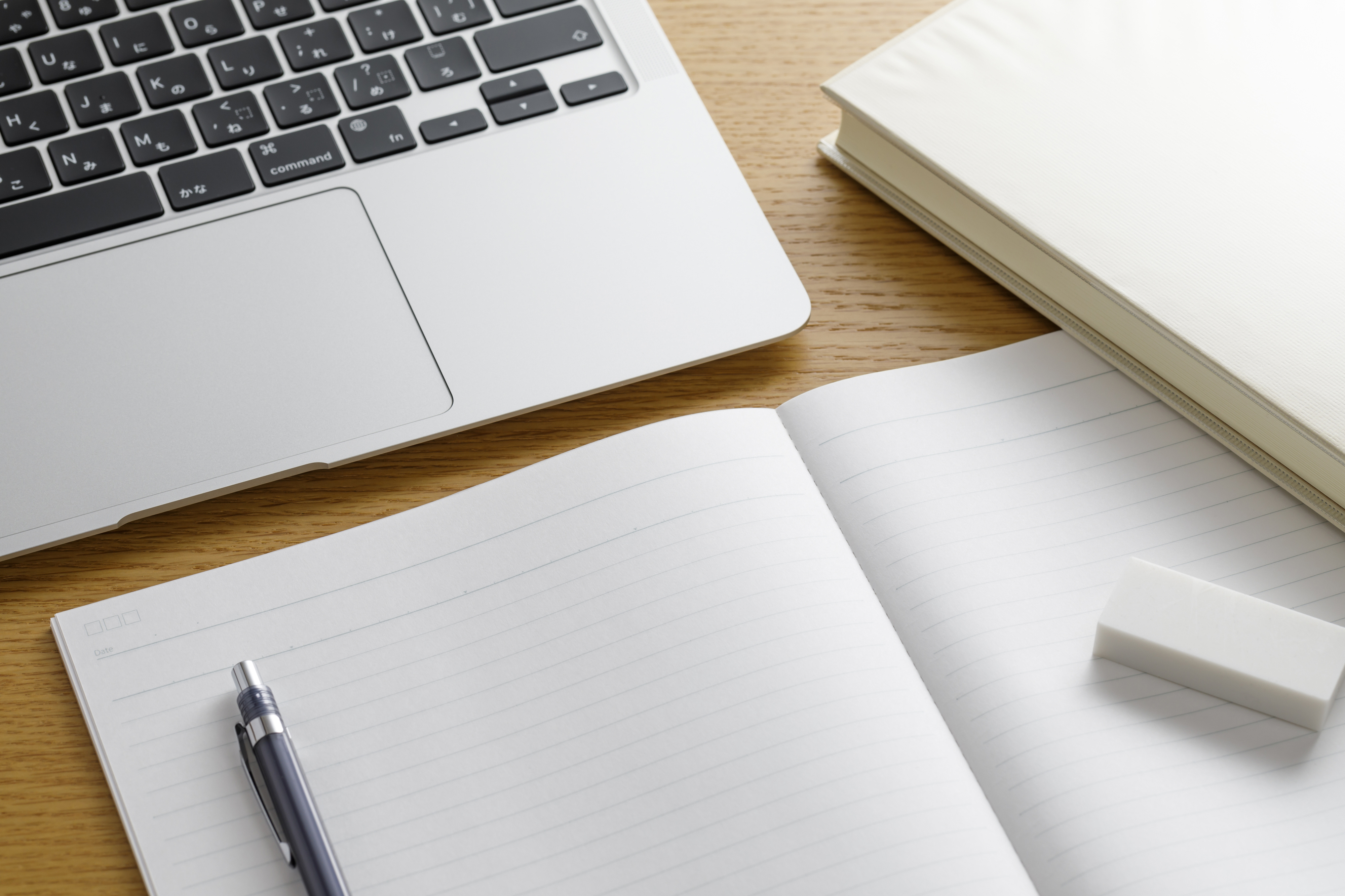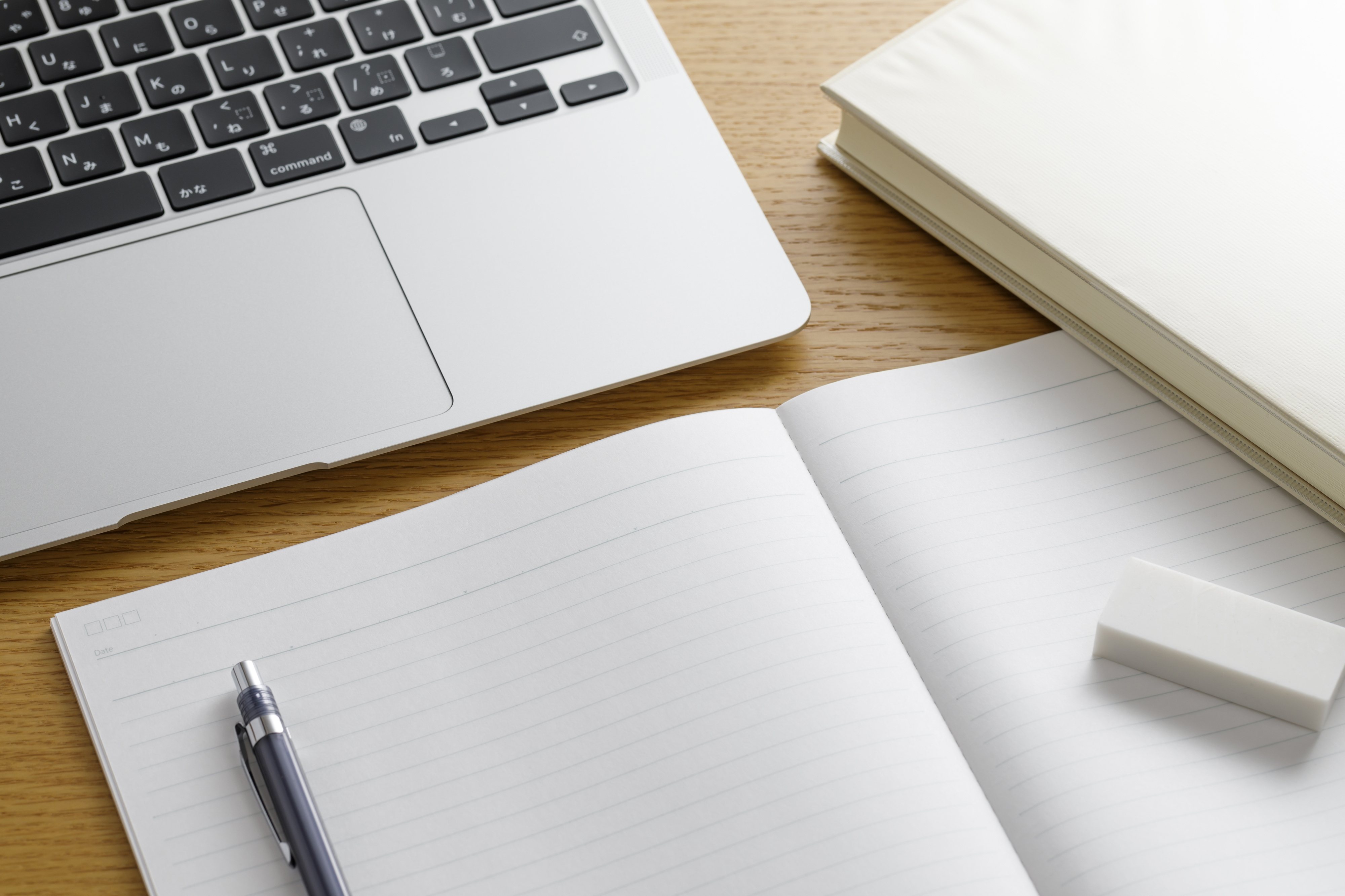【探究への道 第48回】丹治哲之介先生(茨城キリスト教学園中学校高等学校)

「大人とは?」の問いに向き合う3年間の探究活動

丹治哲之介先生
この記事から分かること
-
教育目標から逆算した年次ごとの探究設計
-
探究のテーマ設定における「漠然性」の意味
-
キャリア教育との接続に向けた探究の工夫
総合学園における探究の取り組み
本校は茨城県日立市にある男女共学のミッションスクールで、中学校、高等学校だけでなく、こども園、大学、大学院まで同一敷地内にある総合学園となっています。中高の一貫教育では、教育目標に「心豊かで、実力のある、自立した国際人の育成」を掲げ、これからの社会課題に応えられるような生徒を育てています。
議論の中で生まれた「大人力」という言葉
校内で本校の教育目標について議論をしていた際に、「大人力」という言葉が生まれました。よく先生は生徒に、「大人になりなさい」と言いますよね。しかし、生徒に「大人とは何か」と聞かれると回答に困るはず。なぜなら、その答えは大人ごとに異なるから。だからこそ、高校生のうちから多様な大人との出会いが重要になると思います。多様な大人との出会いの中で自分はどう生きていきたいかを考え、「生きる力」の成長につながるのではないでしょうか。そこで本校の探究活動では、「大人とは?」という問いを3年間かけて探究していくことに決まりました。
「大人力」の獲得に向けた各年次の目標
生徒に「大人力」を身に付けさせるために、学年ごとに以下のような目標を決めました。
1年次の目標は、さまざまな人との関わりから「大人とは?」という大きな問いに対して自分なりのイメージをつかみ、自らの進路についての方向性を考えることができるようになること。親や親戚をはじめとした身近な大人だけでなく、卒業生や教員、地域の方々など、さまざまな大人の生き方を学ぶ、知るという活動を行っていきます。
2年次の目標は、地域や世界に関して自分なりの課題意識をもち、自らの特性を生かしつつ、多くの人たちと関わりをもちながら動き出すことができるようになること。1年次で学んだ自分の特性を生かしながら、実際に地域課題の解決に向けたアクションを起こす活動を進めていきます。
3年次では、2年次までの活動を報告書として言語化するとともに、「自分の将来を切り開けるようになる」を目標に、自分の進路実現という形で「大人とは?」の答えを出していきます。

▲ 「他者と触れ合う」をテーマに参加した地域のイベントにて、来場者にアンケートの協力を依頼している様子。
漠然としているからこそ突き詰める価値のあるテーマ
探究活動を設計するうえで、特にテーマの設計が重要だと感じています。本校の場合、前述の通り、「大人とは?」という漠然としたテーマをキーワードに探究を設定しています。「大人とは?」は、誰でも何となくイメージはつくけれど、人それぞれで捉え方や説明が異なる言葉。この「答えが一つでない」という点が、生徒・教員・地域の大人とを結ぶ本校の探究活動のキーワードとして大いに役に立っていると感じています。
また、目標から逆算しながら学年ごとに活動の目的を明確にすることも意識しています。1年次はインプット、2年次はアウトプット、そして3年次はそれらをまとめ・生かして進路実現につなげる。活動の目的を明確にすることで、生徒は活動しやすく、われわれ教員は具体的な支援がしやすくなったと感じています。

▲探究活動のまとめとして実施された「マイ・プロジェクト発表会」の様子。
教員間の連携とプレーヤーとしての役割
探究の成功のカギは、やはり教員陣の連携だと思っています。一部の先生が自分一人で頑張るのではなく、みんなで作り上げる、全員が「自分事化」できるようにすることが重要だと思います。その中で、活動の核になる先生は、そのための仕掛けづくり、つまり、他の教員を巻き込んで、プレーヤーにしてしまう工夫を行うことが重要なのではないでしょうか。
茨城キリスト教学園中学校高等学校
https://www.icc.ac.jp/ich/