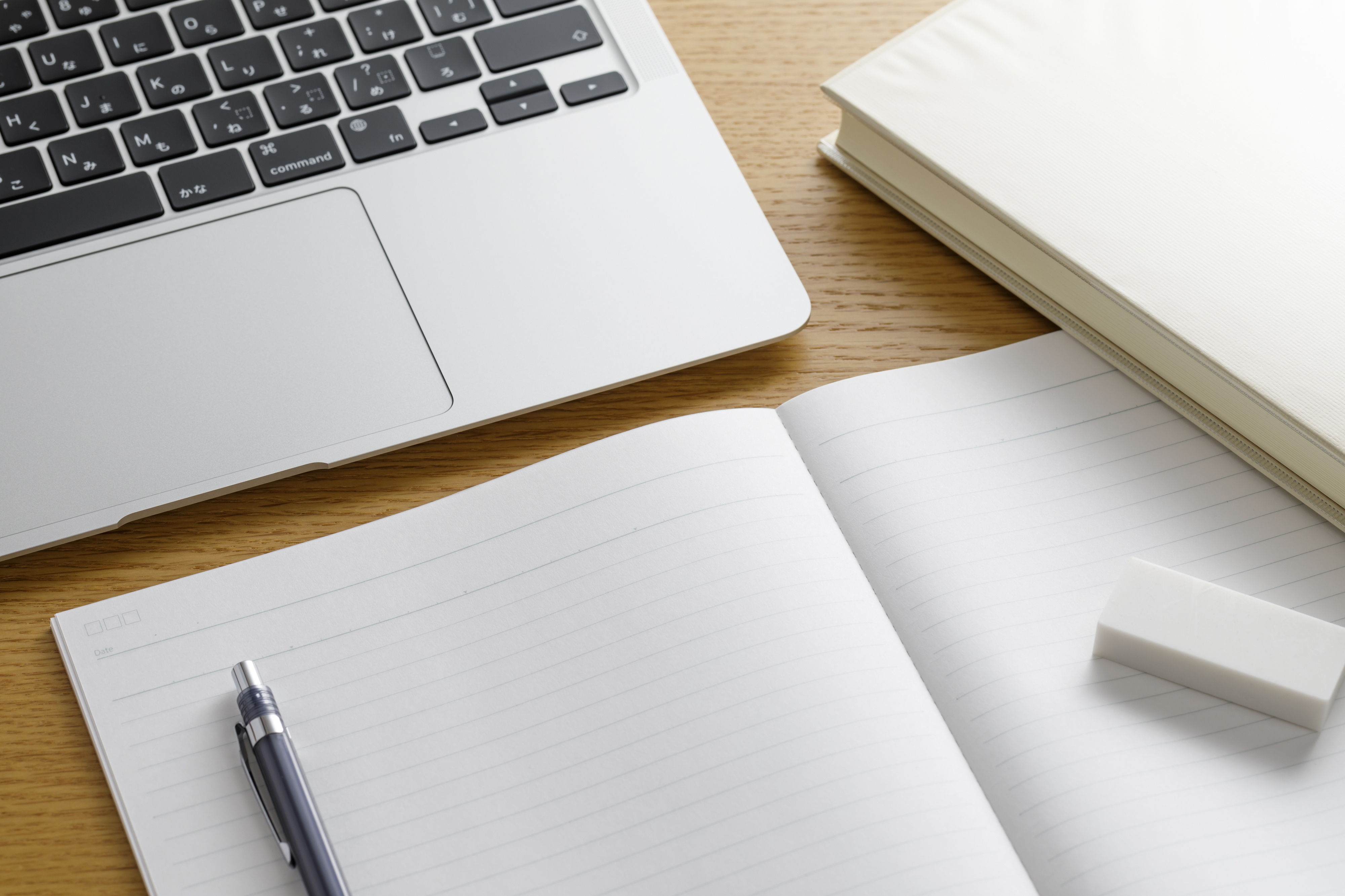【探究への道 第46回】川森憂人先生(三重県立桑名高等学校)

未来を切り開く力を育む課題研究

川森憂人先生(三重県立桑名高等学校)
この記事から分かること
-
SSH指定校として実践する「課題探究能力」を育む探究活動
-
上級生と下級生の縦のつながりによる学び合いが育む主体性
-
持続可能な探究活動を実現するための工夫
生徒の未来を切り開く課題探究能力を育む課題研究
本校は創立110年を超える歴史のある学校です。全日制課程と定時制課程があり、全日制課程には普通科、理数科、衛生看護科・衛生看護専攻科の3学科が設置され、合わせて1,000名を超える生徒が在籍しています。
2018年度から、「地球の未来の先駆者となる科学技術人材」の育成を研究開発目標に掲げ、文部科学省よりスーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定されました。さまざまな課題に対して自ら考え挑戦し、未来を切り開く力を「課題探究能力」と位置付け、その育成に向けた取り組みを進めています。
教員は生徒の伴走者
探究活動では生徒の主体性を重視し、教員はあくまでも伴走者として指導に当たっています。課題研究を進める中でうまくいかないこともありますが、生徒が可能な限り自分たちの力で解決に導けるようにサポートしています。また、研究テーマについてはSDGsの17の目標を念頭に置き、世界で起きている出来事を「自分ごと」として捉え、将来の地球規模の課題解決に向けた意識を醸成しています。
縦のつながりが育む主体性
本校では主体性を育む取り組みの一つとして縦のつながりを大切にしています。具体的には、上級生から下級生に向けて
課題研究の指導を行う機会を設けています。この取り組みは少しずつ効果を表しており、教員が設定した機会以外にも
放課後などにおいて主体的に交流する姿が見られるようになりました。
生徒の興味・関心を刺激するサポート体制の構築
理数科では、物理・化学・生物・地学・数学・情報・医療保健・人文社会科学の8分野に分かれて研究活動を行っています。本校のSSHの課題研究については、運営指導委員として各研究室に対応した専門家の方々にご担当いただいています。このように各生徒の研究内容に必要に応じて指導・助言をいただける体制を構築しており、これまで理数科にとどまらず、他学科においてもご尽力いただいております。
探究を持続可能な取り組みにするために
探究活動を持続可能な取り組みとするためには、教員の負担を軽減することも重要です。そのために、初めて担当する教員の不安や負担が大きくならないよう、指導・評価方法などを具体的にまとめ整理した課題研究指導の「スタートアップガイド」(記事の最後に記載のリンクから実物をご覧いただけます)を作成し活用しています。また、週に一度の打ち合わせや月に一度の会議にて教員間の情報共有を密に行うことで、指導方法などに変更が生じた場合でも、迅速かつ柔軟に対応できるようにしています。
連携と協働で広がる探究
探究活動の取り組みには多種多様な手法があります。私自身、探究活動の担当者として右も左も分からないままスタートしましたが、校内の先生方や大学・企業の専門家の方々など多くの方々に助けていただきました。また、他校で探究活動を推進されている先生方と情報を共有することで、互いの取り組みをさらに進展させることができました。今後も多くの方々と協力し合いながら、生徒の成長に少しでもつながるよう取り組みを進めていきたいと考えています。
三重県立桑名高等学校
https://www.kuwana-h.ed.jp/top.html
SSH活動の様子
https://sites.google.com/mie-c.ed.jp/kuh-ssh/ssh%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AE%E6%A7%98%E5%AD%90
課題研究指導「スタートアップガイド」
https://sites.google.com/mie-c.ed.jp/kuh-ssh/ssh%E6%95%99%E6%9D%90