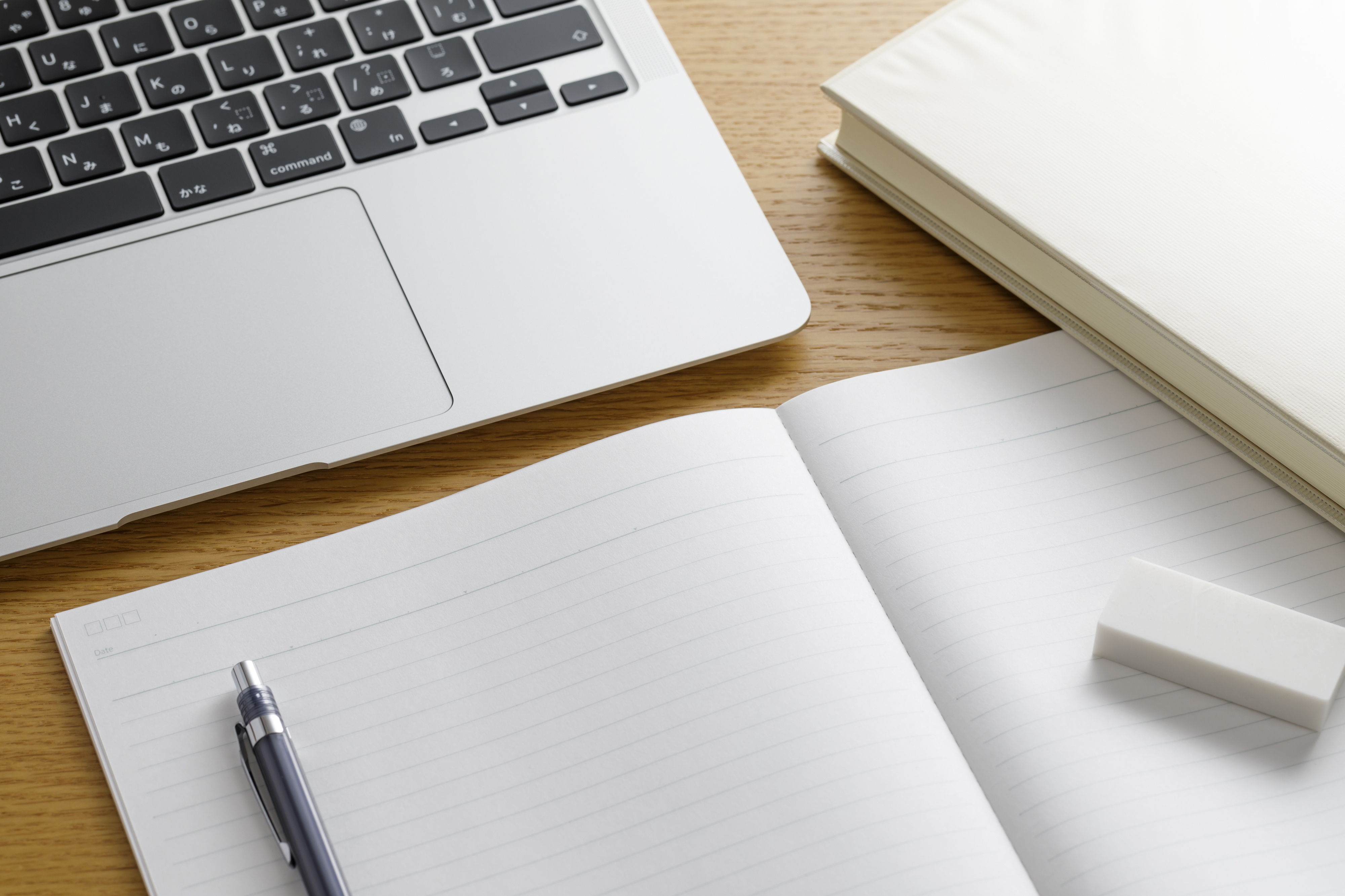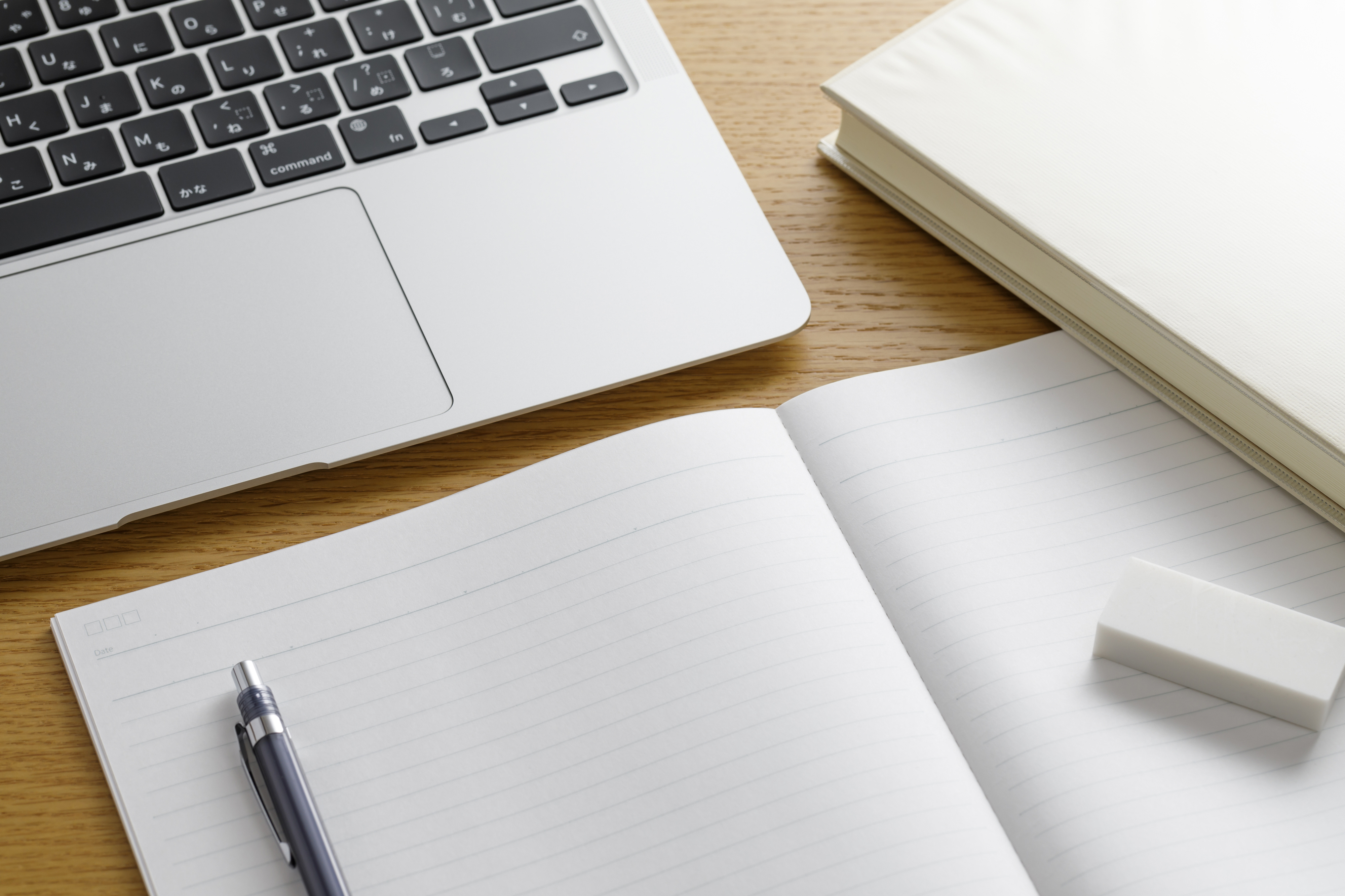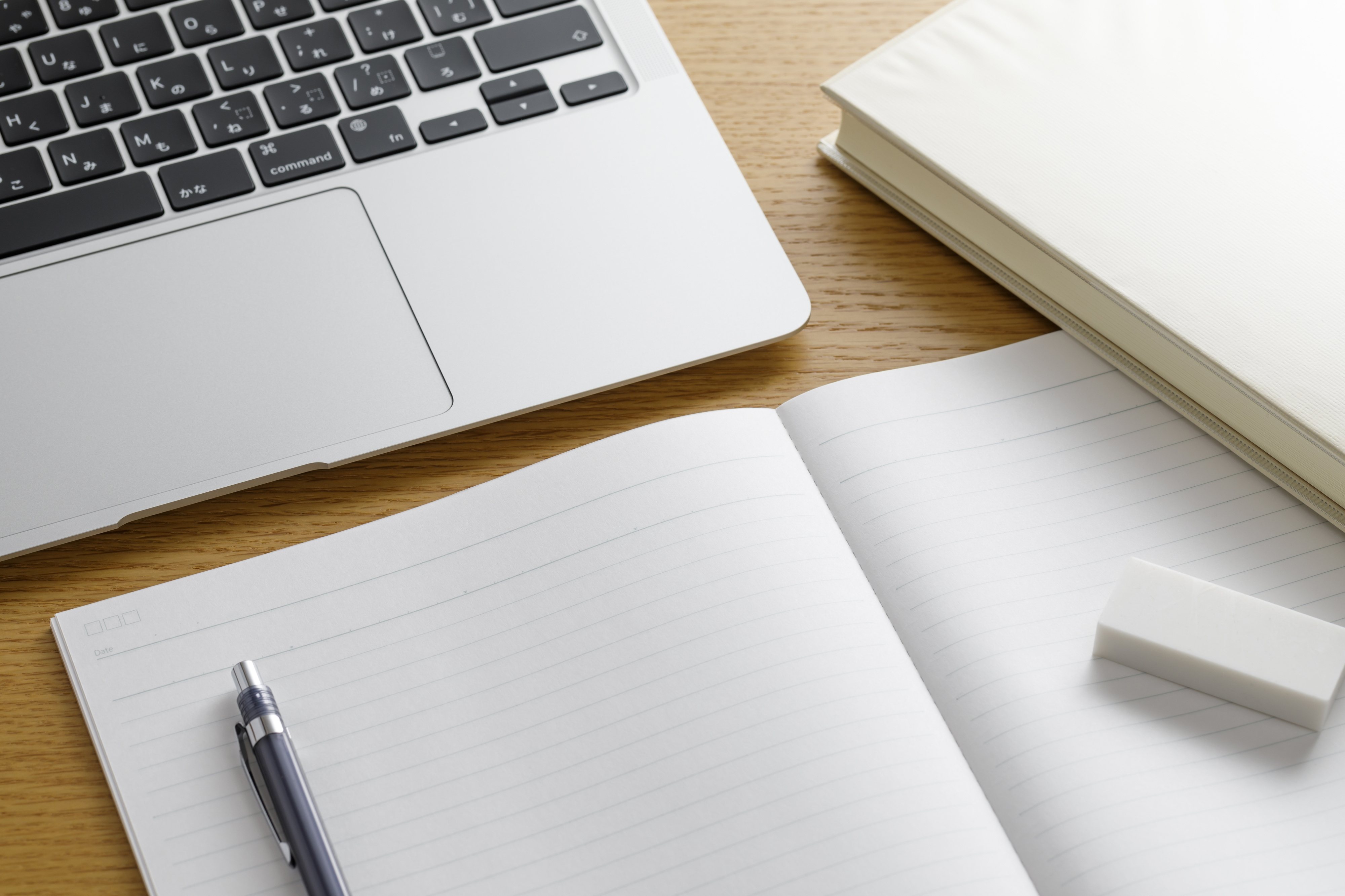【探究への道 第47回】宮崎芳史先生(新潟県立新潟南高等学校)

自燃性・自走性を育む探究の仕組みと文化づくり

宮崎芳史先生
この記事から分かること
-
生徒の自燃性や自走性を育む先生の姿
-
“have to”から“want to”へと転換する学校づくり
-
課外活動と連携しながら探究を発展させる仕組みづくり
20年以上蓄積していた探究的な学び
本校のスクール・ミッションは「探究的な学びにより、様々な分野でリーダーとして活躍できる人材を育成する学校」です。
2003年度からスーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定され、2025年度からは認定枠として20年以上にわたって探究的な学びを推進。伝統を生かしながら、学校全体として探究活動に積極的に取り組んでいます。
生徒の「自燃性」と「自走性」を育む
私が探究活動を通して育みたいのは、「自燃性」と「自走性」です。生徒は言われたことを的確に実行することが得意で、優秀ではあるものの、受け身の姿勢が目立つのも事実。
心に火が付き、主体性をもって社会へと羽ばたいていく生徒が少しずつ増えていけばと願っています。また、学校全体としては「課題発見力」「仮説設定力」「計画力」「実証力」「考察力」「表現力」といった探究力の育成に力を入れていますが、それだけでなく、自分の思いや夢を大切にする姿勢も重視。学年目標として掲げる「Canvas」には、自分の未来を自ら描き、それを実現していってほしいという願いが込められています。探究活動の時間が主体的な「越境」「創造」「表現」「自己変容」の時間となればと考えています。

▲ 大学生や社会人との対話・コーチング(しつもんクエスト)を通して、探究の「自走性」を高める「探究STARTUP」の授業風景。
生徒の‘‘want to”に光を当てる学校づくり
また、「ブレーキをかけない学校」づくりも重視しています。勉強・課題・部活など“have to”に縛られるのではなく、「やってみたい」「やりたい」という“want to”に時間をかけられる余白を意図的に生み出すこと、「こんなことをやってもいいんだ」「探究って(熱中・没頭できる)青春だ!」と思える環境をつくっていくことが重要だと考えています。それには、探究を応援する教員や保護者のメンタルモデルの変容も不可欠。探究が進路や入試につながる事例が見えてくると、保護者も教員も安心して探究を応援できるようになり、結果、より生徒の挑戦を後押ししてくれるのではないかと感じています。
▲ 生徒の好きなダンスと課題解決(海岸清掃)を組み合わせた「海にかける! アオハルプロジェクト」の様子。
生徒は楽しみながら、地元の海を素足で駆けられる環境をつくるという目標の下、探究活動に青春を懸けた。
実践型探究「マイプロジェクト」が生んだ広がり
私は現任校に赴任した2020年度に初代実行委員長として仲間とともに「NIIGATAマイプロジェクト☆LABO(以下、NIIGATAマイプロ)」を立ち上げ、主体的な課外活動である実践型探究マイプロジェクトの新潟県Summitを主催。思いのある多くの社会人・大学生と新潟県の高校生をつないできました。5年間で大学生も含めて全県で200以上のマイプロジェクトが誕生。私自身が校外・課外で「越境」「探究」「挑戦」「自己変容」し続けてきた日々でしたが、その経験と築いてきた学びの生態系を校内でも実践に少しずつ移すことができるようになってきたと思います。
赴任当初、マイプロジェクトは希望者の有志活動として、生徒も私も授業時間以外の時間を使って取り組んでいました。2年目に、2学年の探究活動の時間に課題研究だけでなく実践型探究のコースを創設して以来、学年にもよりますが希望者は、授業でもマイプロジェクトに取り組める環境が整いました今年度は、2年生の60名以上がマイプロジェクトなどの実践型探究に取り組んでいます。熱心に活動をした先輩たちの中に総合型選抜入試で驚くような成果を出した生徒がいたこともあり、今は外部の方と連絡を取ったり、外部で活動をしたり、積極的に越境する生徒たちを多くの先生が応援してくださるようになり、本当にありがたい限りです。また、今年度からはNIIGATAマイプロに講演やコーディネートを依頼できる体制もつくられ、学校としても外部の人材と協働しながら現在の探究活動の取り組みを継続できる仕組みづくりを目指すことができています。
▲ 対話型のアート鑑賞とファシリテーションを学ぶ「ART CONNECTプロジェクト」の様子。
生徒は感性・創造性・コミュニケーションを育む教育や、楽しさを感じられる学びの在り方について模索し、社会へ発信した。

▲アルビレックス新潟レディースと連携した「私から始まるサカマチプロジェクト」の様子。
「プロサッカーチームが新潟にある」という魅力を多くの人に届け、ファンを増やすべく活動中。
思い通りにいかないことも喜ぶ
自己決定を促し、主体性に委ねることは、ときに忍耐強さが求められます。主体性に委ねるからには、意欲的に活動しない(何もしない)自由も認める必要があります。こちらの意図に反した決断をしても、それを尊重しなければなりません。ときに生徒の代わりに頭を下げる場面も生じます。それでも、やはり生徒の主体性に委ねたい、と私は思います。思いもしなかった大きな成果をあげる生徒ほど、自走力が高いからこそ、大人が事前に思い描いたようには動いてくれないものです。そして、高校生ですから、そのような生徒ほど、未熟さが目立つこともあります。先生方から見れば、思い通りに育っていないと感じる生徒かもしれません。しかし、そんな生徒と出会ったときにこそ、何が起こるかわからない偶発性を楽しむ気持ちで生徒と関わることで、思いがけない面白い探究活動が生まれるものだと私は考えています。多くの高校生は自分の思いより、大人の意図に従おうとしてしまうものです。大人に対してではなく、自分に素直になれる時間が探究活動の時間なのだと思います。
新潟県立新潟南高等学校
https://niigatami-h.nein.ed.jp/
NIIGATAマイプロジェクト☆LABO
https://www.niigata-mypro-labo.com/