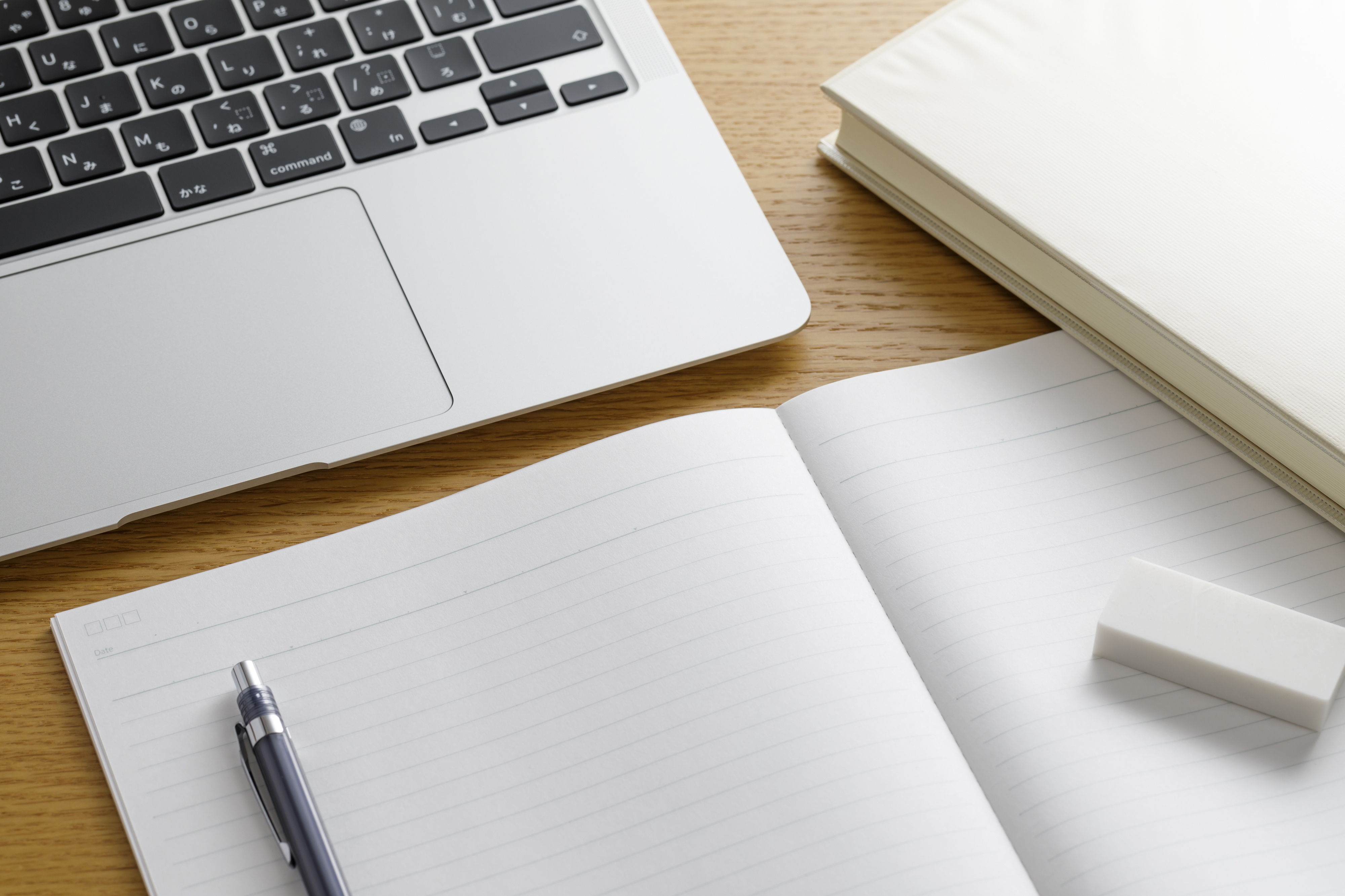【探究への道 第44回】大沼克彦先生(秋田県立大曲農業高等学校)

.jpg?width=333&height=295&name=%E5%85%88%E7%94%9F%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%86%99%E7%9C%9F(%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0).jpg)
本校は創立133年を迎える秋田県で2番目に歴史のある高校です。「農業教育を通じて豊かな感性と人間性を育み、社会や時代に即応する人材を育成すること」が教育目標であり、農業科学科、食品科学科、園芸科学科、および生活科学科の4学科で、それぞれに特色のある学習活動をしています。
秋田県では、目指す教育の姿「ふるさとを愛し、社会を支える自覚と高い志にあふれる人づくり」を達成するための最重課題のひとつに、「『問い』を発する子ども」の育成があります。探究型学習はまさに生徒の「問い」から始まる学習活動であるため、各学科の教員が精力的に取り組んでいます。
私が探究型学習において心掛けているポイントは、失敗を分析し、改良することで目的が達成できることを生徒に実感させることです。実験には正解があり、期待通りの結果がでれば○、そうでなければ×という意識が生徒にも教員にもあり、「失敗=悪」というイメージも根深く存在します。したがって、予想が当たらない、予想通りの結果が出ない実験は自分たちの技術の未熟さと理解不足の結果としての失敗であり、そこから何かを得ることはないと考えているようです。
何かを成し得ようとも失敗することがほとんどで、いわば失敗は当たり前。失敗の原因を特定し、改善することではじめて本来の目的に到達できるものの、それを十分に理解できていない生徒が多い印象を受けます。そこで本校では、探究型学習のなかで、失敗から原因を生徒が主体的に分析・改良することで成功に向かえるよう、教員一同サポートをしています。
私が担当する探究型学習に「人為的に酸性化した湖の水を電気分解という方法を使って中性にする」という研究があります。詳細は割愛しますが、実験を重ねて先輩から後輩へデータ10年以上受け継ぎ、実験当初は1,000 ml/hで中性にしていたものを230,000 ml/hにまで引き上げることができました。これまでの研究結果については、秋田県仙北市にあるクニマス未来館に常設されています。
▲ 課題研究の時間に試薬を調製している様子
.jpg?width=567&height=331&name=%E5%B8%B8%E8%A8%AD%E5%B1%95%E7%A4%BA(%E3%81%BC%E3%81%8B%E3%81%97%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E3%81%82%E3%82%8A).jpg)
▲ クニマス未来館(秋田県仙北市)の常設展示
もちろん、実験に参加してきた生徒の努力には目を見張るものがあります。しかし、彼らの努力だけでなく、研究に賛同し協力してくださった大学の先生や、地域の自治体や住民の皆さまの力添えがあったからこその結果だと考えています。このような体制の中で、研究に目覚めて研究者を目指して大学進学する生徒が育つ場合もあり、研究畑からこの業界に入った身として、こうした生徒の進路選択・実現をとても嬉しく思っています。
特に本校のような農業高校は地域とのつながりが強いため、生徒は地域の課題に気付きやすく、解決の意欲も高い印象を受けます。高校生の目線で地域の課題を見付け、高校生の視点で課題解決に向けた取り組みを進め、一度や二度の失敗などで諦めることなく、失敗を「善」と捉え、改良を重ねながら課題の解決に近付く実感をさせることが重要なのではないかと思っています。課題解決に向けた地域の方々と高校生の協働的な活動は、高校生の課題解決能力はもちろん、コミュニケーション能力や地域での役割意識を高めることにも寄与します。そして、生徒はその過程で自身の在り方、生き方を考えることができるようになるのではないでしょうか。
秋田県には博士号を有し、探究型学習の指導に長けた教員がたくさんいますので、探究でお困りの際は以下のリンクよりお問い合わせください。
秋田県立大曲農業高等学校
https://daino-hs.net/
博士教員教育研究会
https://akitaphd.wordpress.com/