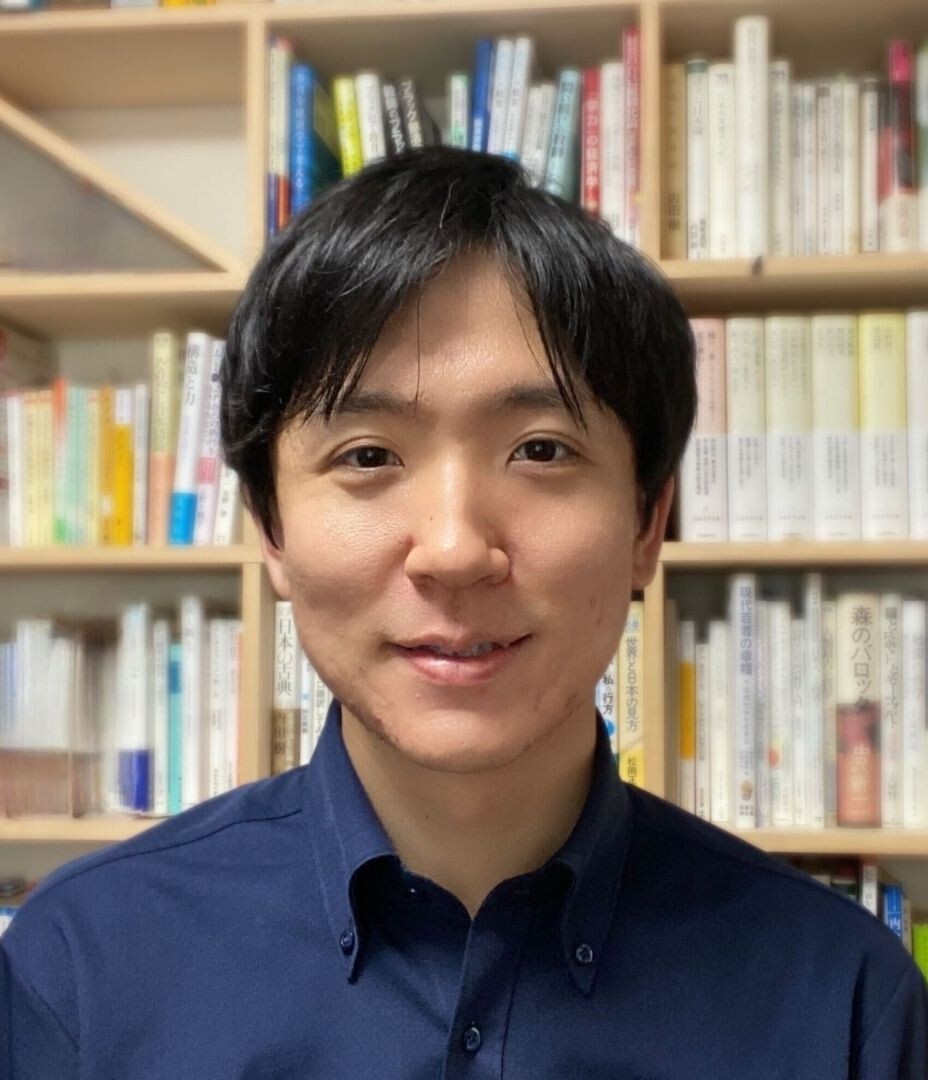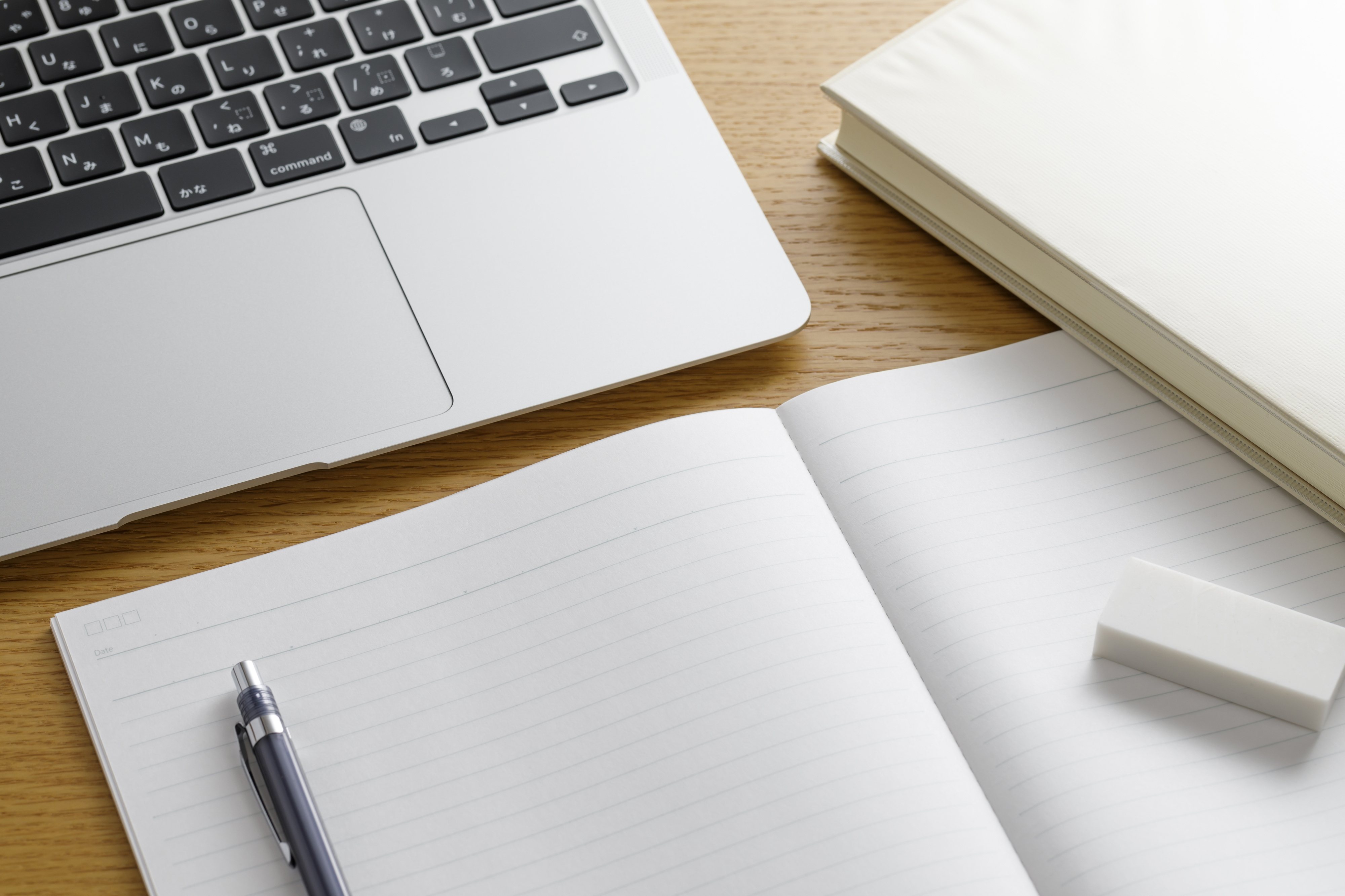【探究への道 第36回】大橋優生先生(佐野日本大学中等教育学校)

「やり取りの多さ」と自由なテーマで「あと伸び」力を育む探究型学習」

佐野日本大学中等教育学校 大橋優生先生
この記事から分かること
-
「好き」を基点に「あと伸び」を支える力を育む探究型学習
-
探究活動を支える3つの柱(自由なテーマ、縦割り探究、高大連携)
-
鍵となる「やり取りの多さ」を実現するうえでの課題とその解決
探究型学習のねらいと探究を深める鍵
栃木県佐野市にある本校は、日本大学の付属校であり、6年間のカリキュラムの中で選択肢 を幅広く残しながら学ぶことができる利点を生かした教育を日々実践しています。探究活動 の目標は、生徒の「あと伸び」を支える幅広い力を育むことです。自分の「好き」を基点に 深く考え実践することを通して物事を多角的に判断できる人材を育てたいと考えています。
探究を深めるために特に重視しているのは、生徒間や教員とのやり取りの機会を最大化する
ことです。他者との対話を通じて新しい視点や意外な関係性に気づくことが、探究を深める
重要なステップだと考えています。
探究活動の3つの柱
本校の探究活動には、以下の3つの特⻑があります。
1. 教員の趣味や特技に基づいたテーマから生徒が自由に選択
2. 学年を越えた縦割りグループでの探究
中学1年生から高校3年生までが混在する縦割りグループで探究を進めています。異なる世 代間のギャップは探究を深める良いきっかけになります。
3. 高大連携の活用
日本大学との連携によるオンライン指導や大学施設の訪問を通じ、大学の先生方のお力も借
りながら探究活動を進めています。この専門家とのやり取りも探究を深めるうえで欠かせな
い要素となっています。
「やり取りの多い」探究実現に向けた課題とその解決
他校にはない自由度の高い探究活動を実現できたと自負していますが、この構築には多くの
課題がありました。特に、探究活動を進めるうえで「やり取りの多さ」を鍵にすると多くの
教員の協力、そして学内でのビジョンの共有が不可欠です。「生徒も教員も楽しむ」ことを
念頭に置き、お互いの興味や関心をすり合わせることで現在の形にたどり着きました。モッ
トーは「好きこそ物の上手なれ」。これに尽きるのではないでしょうか。

.jpg)