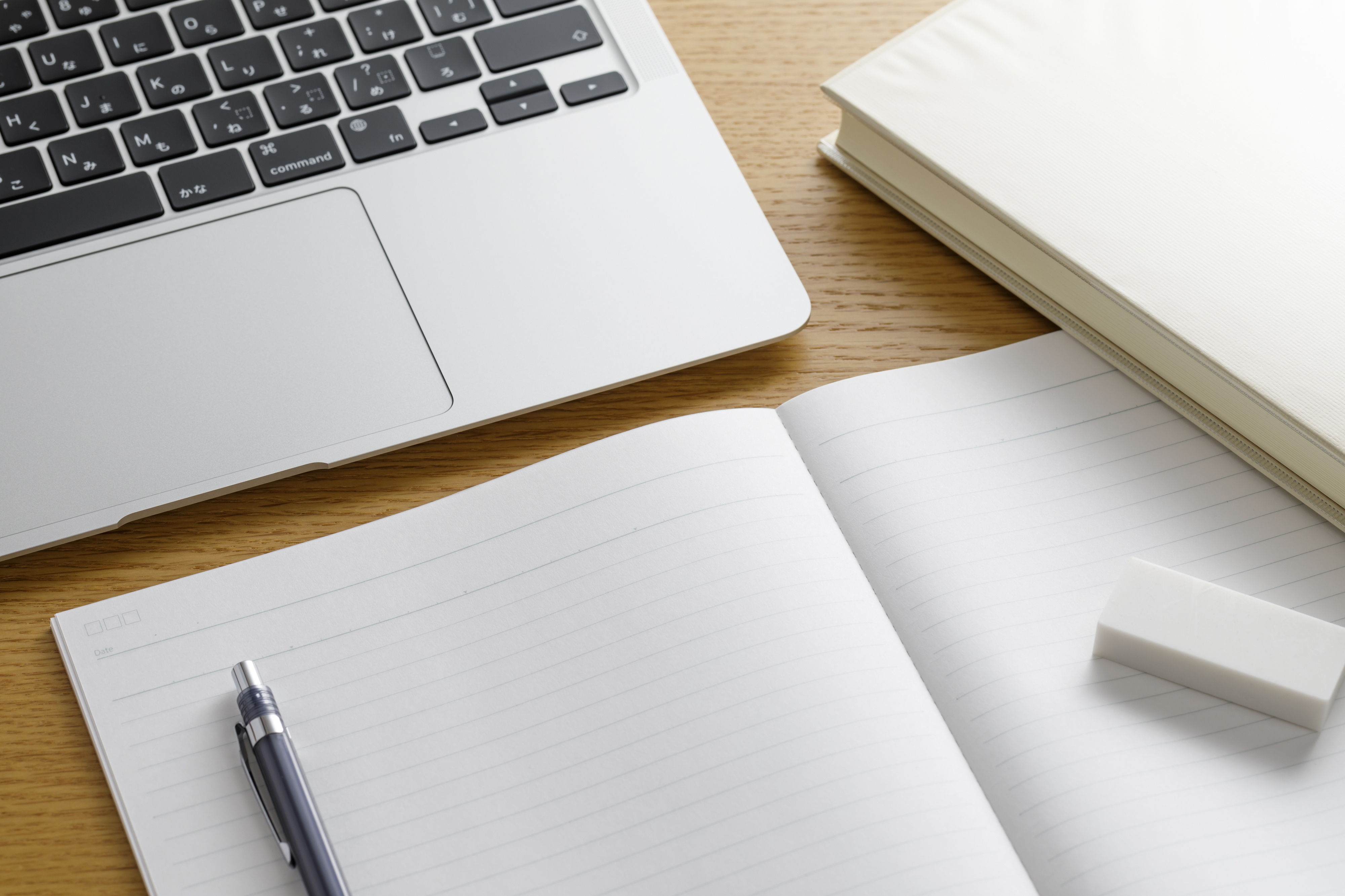【探究への道 第45回】鳥居正洋先生・樫本英人先生(長崎県立長崎東中学校・高等学校)

本校は、長崎県にある公立の併設型中高一貫教育校で、普通科と国際科を設置しています。「WWL(ワールド・ワイド・ラーニング)コンソーシアム構築支援事業」の拠点校、また三菱みらい育成財団の「心のエンジンを駆動させる教育プログラム」に指定を受け、「『世界の平和と共生』に貢献するイノベーティブなグローバル人材の育成」をテーマに掲げながら、先進的で特色ある教育活動を実施しています。令和6年度からは、「高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)」として、デジタル時代に対応した学びの改革を加速させています。
また、同年には「長崎県イノベーションハイスクール」にも指定され、授業日でも休業日でもない“第3の学びの日”として「ひがしチャレンジデー」を導入しました。この特別な1日は、生徒と教員が自ら時間の使い方を考え、「学び」「休息」「挑戦」のバランスを自律的にデザインする新しい教育実践です。
それでは、本校の「学び」の特色であるWWLとDXの取組について、各担当よりご説明します。
【WWL・三菱みらい育成財団 事業概要】 WWL探究推進室長 鳥居 正洋

(1)学校設定目標の策定(WWL7)
上記の「『世界の平和と共生』に貢献するイノベーティブなグローバル人材の育成」を果たすため、本校ではその人材に必要な資質・能力を、7つの力(WWL7)として定義し、学校設定目標として位置付けています。「課題発見・解決力」「創造力」「情報分析・活用力」「自己表現力」「協働性」「学ぶ意欲」「地球市民性」の7つです。この力の育成を、探究学習をはじめすべての教育活動を通じて行います。
探究学習はともすれば、手段が目的になりがちです。あくまで目的は生徒の育成にあることを、教師・生徒ともに共通理解を図り、目指すべき力という本質が揺らぐことがないようにしています。また、このWWL7については、独自に開発したルーブリックにて年度当初と最後に生徒が自己評価を行い、自らの力の伸長度を把握して、自己肯定感の醸成を図っています。また、外部による思考力評価とのクロス分析を行い、生徒の実態把握に用いています。

▲長崎県立長崎東中学校・高等学校のグランドデザイン
これらの力は多様な協働ネットワークのなかで培われます。本校は令和2年度のWWL指定時より、国内外の高校、大学、企業、NPO等、350以上の協働機関と連携してきました。外部協働による、本校独自の学際的な学びのネットワークを構築しています。

▲学際的な学びのネットワーク
(2)探究活動の体系化
本校の教育活動のコアである探究学習は、中1から高3までの6年間の活動を体系化しています。被爆地である本県の小・中・高・特別支援の各種学校は、平和教育を行うことが一般化している土壌にあります。本校中学校で推進される平和教育をSDGsへと広げ、高校の探究での社会課題の設定へとつながっていきます。戦争や核軍縮というテーマをコアに、環境やジェンダーなど、「広義の平和」へとそのテーマを広げていくイメージです。最終学年である高3では「高校生国際平和会議」を開催し、これまで培ってきた知識や人間力を、国内外の高校生と世界課題について議論するなかで存分に発揮します。アウトカムを得ることで、さらに高度で深い学びを得るとともに、社会に対する自己の有用性を獲得し、グローバル人材としての自覚を強めていきます。

▲中高6年間の探究学習を体系化
また、令和7年度は、三菱みらい育成財団主催の探究全国大会、「高校生MIRAI万博」にて本校の探究チームが最優秀賞(第1位)、優秀賞(第2位)を受賞し、日本一を達成しました。この2チームは、本年7月31日に大阪万博会場で代表発表をすることが決定しています。生徒が主体的に取り組んできた探究成果を、世界に発信する機会をいただいたことを、大変ありがたく感じています。

▲探究の全国大会で日本一を達成(最優秀賞 『Critical Thinking for Peace』)
(3) Study Tour(スタディツアー)
本校では、上述した協働機関をはじめ、各所への生徒のフィールドワークを推進しています。特に探究的な学びを深めるべく、特別なスタディツアーを用意しています。ベトナム、ニューヨーク、ハワイ、カリフォルニア、三菱重工、広島、沖縄、東京(東京大学、国連大学)において、選抜された生徒を対象に実施し、一流の学識者との出会いにより、学際的で高度な学びを体感しています。
 ▲スタディツアー(令和6年度実施分)
▲スタディツアー(令和6年度実施分)
 ▲東京大学スタディツアー
▲東京大学スタディツアー

▲ニューヨークスタディツアー
令和7年度の目標は、探究学習の『完成』です。もちろん教育の世界に『完成』などありえませんが、しかしながらそこを目指していきたいと考えています。探究学習をパッケージ化し、独自教材を開発すること。全生徒が意欲を持ち、成長する環境を醸成すること。課題は尽きませんが、すべてが挑戦であり、すべてが新鮮な喜びです。生徒と教師、どちらも最高に成長でき、最高に歓喜できる。そのような探究の道を歩んでいく決意です。
【DX 事業概要】 DX探究推進室長 樫本 英人

DXハイスクール採択校としての主な取り組みの一つが、データリテラシー教育の推進です。具体的には、数学において「統計とデータサイエンス」という新たな学校設定科目を導入し、データに基づいて考え、判断し、表現する力を育成しています。さらに、生成AIの活用なども含めた情報活用能力の育成を計画し、生徒の主体的な学びを支えるデジタル環境の整備を進めています。

▲DXハイスクールで整備した「探究ルーム」での授業の様子
こうした取り組みは、「総合的な探究の時間」だけでなく、教科においても探究的な学びを取り入れ、新たな学びを全校的に進めています。生徒が問いを立て、情報を集め、仲間と議論しながら答えを導き出していくプロセスは、まさにこれからの時代に必要な学びの姿です。正解のない問いに挑戦する中で、考える力、伝える力、そして人とつながる力を育んでいます。
長崎県立長崎東中学校・高等学校
https://www.news.ed.jp/higashi-h/index.html
公式note
https://n-higashi-edu.note.jp
長崎東WWL公式Instagram
https://www.instagram.com/wwl.nagasaki.higashi/
長崎東WWL公式Facebook
https://www.facebook.com/wwl.nagasakihigashi/