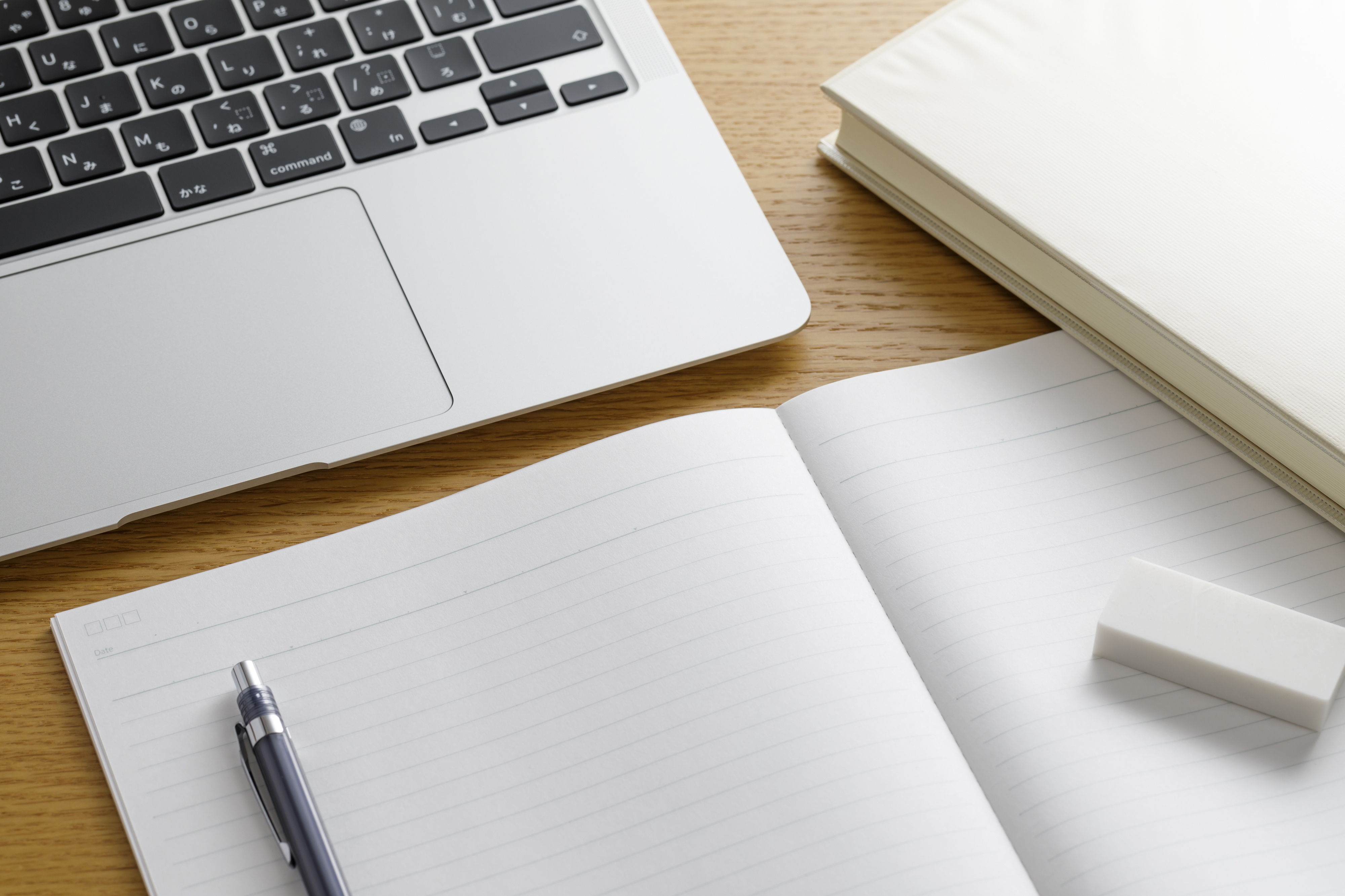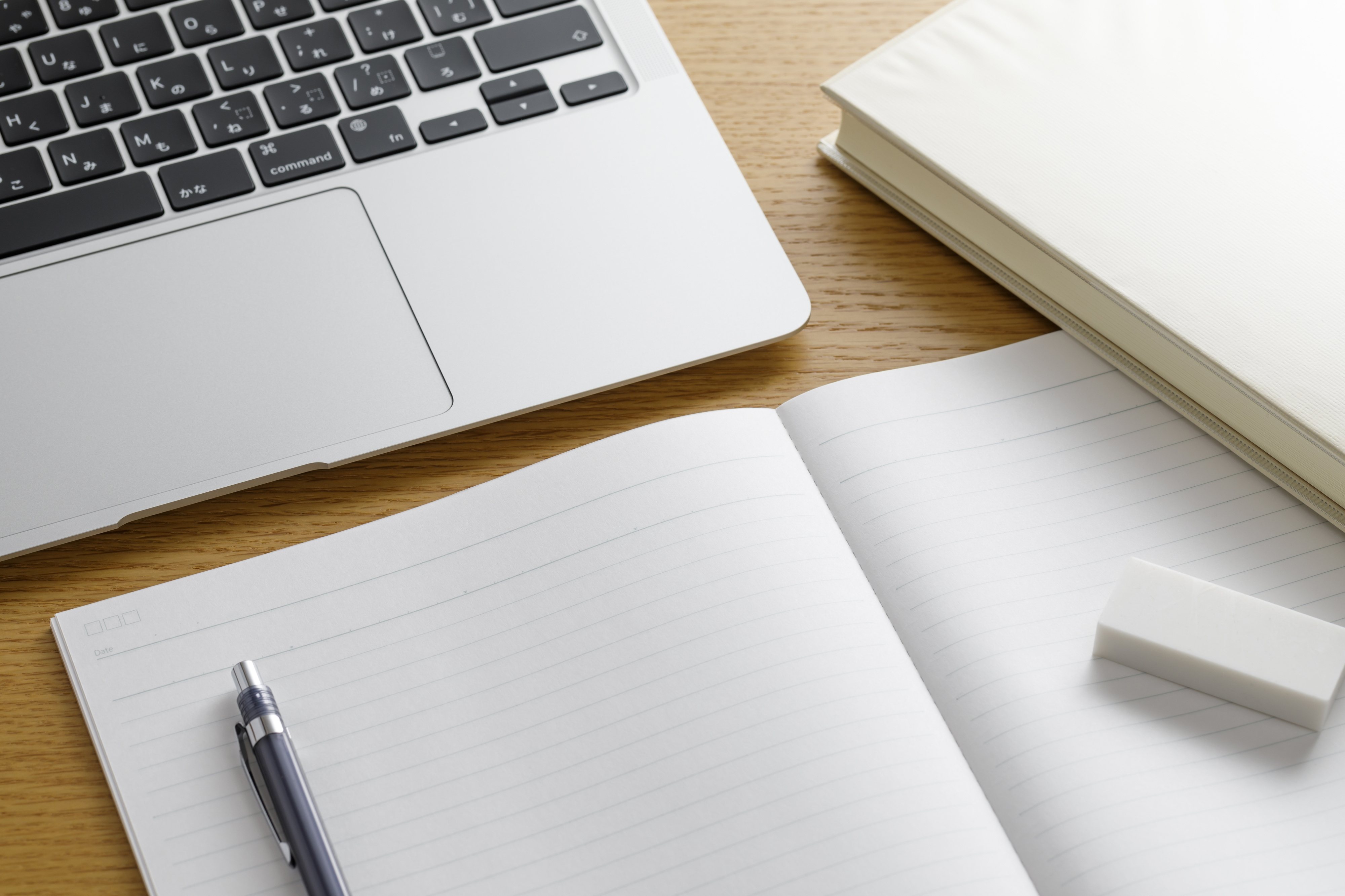【探究への道 第38回】神田正行先生(藤村女子中学・高等学校)

「想像力」と「創造力」を育む探究型学習
この記事から分かること
-
生徒の「想像力」と「創造力」を育むための実践例
-
探究型学習における先生の役割や指導・支援のポイント
-
コース制を生かしたカリキュラムと卒業論文の取り組み方
探究型学習で育成を目指す「想像力」と「創造力」
本校は、92年の歴史を誇る、東京の武蔵野市にある中高一貫の女子校です。開校当時、まだ世に広まっていなかった女性の社会進出や女子教育に着目したその精神を現在も引き継ぎ、変化を恐れず新しい教育に取り組んでいます。
生徒には、未知のモノや現象に対して「知りたい!」という好奇心をもってほしい、想像を膨らませながら自ら疑問を発見し、その小さな疑問を種に創造力を働かせ新たなモノを考案する力を身に付けていってほしいと願い、探究型学習では「想像力」と「創造力」を育むことを目指しています。
探究型学習の伴走者として
これらの力を育むためにわれわれ教員が気を付けているのは、探究学習では、ゴールを知っておきたいという気持ちを抑え、伴走しながら生徒と一緒に答えを探すことです。生徒のアイデアを尊重し、仮説が崩れることも学びの一環と捉え、次のステップを模索する手助けに徹します。同時に、生徒には仮説が立証できないことは失敗ではなく、成功への第一歩であるということも伝えています。
探究型学習の伴走者として
本校ではコース制を採用しており、以下のようにコースごとに探究のテーマが異なります。
- アカデミック・クエストコース:語学を通じて学問を探究する
- キャリアデザインコース:将来設計を考えながらキャリアを探究する
- スポーツウェルネスコース:スポーツやそれを支える人に着目しスポーツを探究する
どのコースでもそれぞれの専門分野の方々と協働、意見交換しながら探究を進め、最終的には生徒自身が専門テーマを設定し、卒業論文を執筆します。その際に重視しているのは「自己完結させず周囲に発信すること」。年度末には多くの人の前でプレゼンテーションすることになりますが、その過程を経て自信を身に付けていってほしいです。
探究型学習における課題と工夫
「総合的な探究の時間」が必修化されて以来、本校ではトライ&エラーを繰り返しながらカリキュラムを構築してきました。特に、学外の方々との協力が不可欠な活動ではスケジュール調整やプログラム継続の難しさに直面することもあります。しかし、答えは一つではありません。われわれ教員も、新たなアイデアを出し合いながら、探究心をもって企画に挑んでいきたいと考えています。
探究型学習で重要な「伴走と放任のバランス」
探究学習においては、教員がファシリテーターとして生徒の側に控えるということを徹底することで生徒の自主性を引き出すことが成功の鍵。伴走と放任のバランスを見極めるのは難しいものの、適切にサポートできれば生徒の好奇心がどんどん広がり、学びが深まります。我々教員自身も未知の世界を楽しみながら、周りの先生方と協力してプログラムや環境を整えていくと良い探究が必ず生まれると思います。
藤村女子中学・高等学校
https://fujimura.ed.jp/