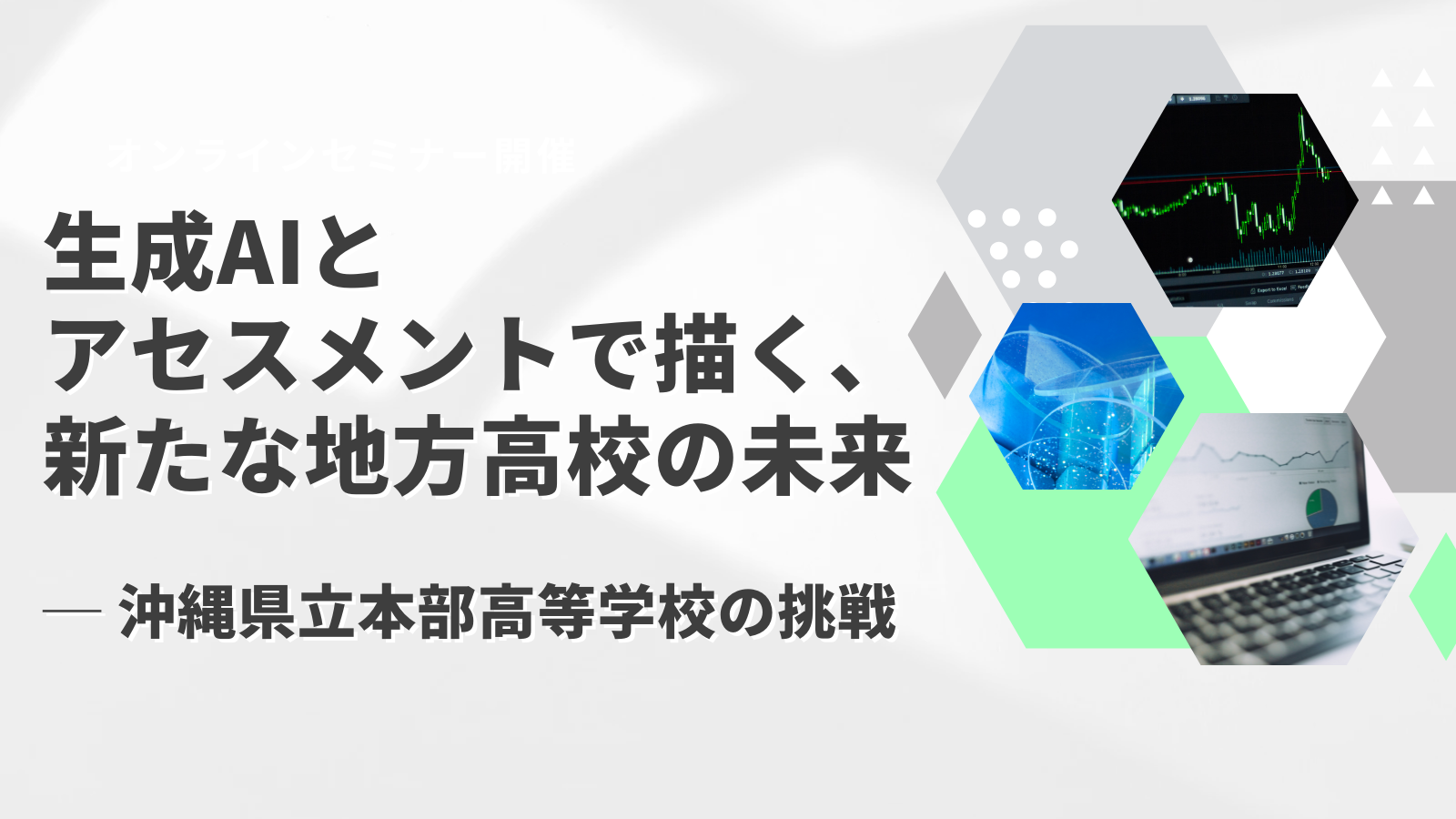探究は「生もの」― 生徒のために、民間企業との新たな協働へ
沖縄県の北部に位置する沖縄県立本部高等学校は、全校生徒150名に満たない小規模校ながら、進学と就職の双方を志望する生徒が在籍しています。多様な進路に応えるために、同校の「総合的な探究の時間」では、先生方が熱心に試行錯誤を重ねてこられた一方で、いくつかの大きな課題にも直面していました。
既存教材とのミスマッチ
出版社や探究プログラムを提供する企業の教材を導入しても、必ずしも生徒たちの興味や実態に合わず、期待する成果につながらなかった。
自作カリキュラムの負担
学校独自で教材を作成し常に内容を更新し続けるには、先生方の負担が大きい。また、評価方法の設計やカリキュラムの効果検証を継続的に行うことにも難しさを感じていた。
同校の津嘉山先生は「探究は『生もの』。生徒の実態に合わせた継続的なブラッシュアップが欠かせない」と語ります。この「継続的なブラッシュアップ」を実現するため、カリキュラムの設計・構築を思い切って外部に委ねるという決断をされました。
ハード面の整備から、学びを深化させるソフト面の充実へ ─ IGSを選んだ理由
同校は令和6年度から、文部科学省の「高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)」に採択されています。初年度は事業予算を活用してハード面の整備を重点的に進め、国内でも先進的なドローンの「二等無人航空機操縦士」の国家資格が取得できる環境を整備されました。
このように、資格取得という明確な成果につなげる一方で、先生方はその先の学びを見据えていました。それは、習得した最先端の技術を、卒業後のキャリアや社会での活躍にどう結び付けていくか。そのための探究的な学びをどう設計し、教材を開発していくかという、ソフト面の充実でした。 そうした中で出会ったのが、弊社の「教育データと生成AIを用いた、エビデンス・ベースの伴走型カリキュラムの共創」という提案です。
具体的には、
データ起点の設計
生徒の資質・能力を可視化しながら同校の特長を生かす「理数」の探究カリキュラムを設計。
伴走支援
弊社スタッフがモデル事業に入り込み、授業と教員研修を同時に実施。
年度サイクルで改訂
アセスメントの結果を踏まえ、PDCAサイクルを回しながらカリキュラムを最適化。
というものです。津嘉山先生は「評価データと指導ノウハウをワンストップで提供してもらえる点が魅力。教材の提供や人の派遣だけでなく、プログラムの効果検証とそれに基づくプログラムの改善まで伴走すると言ってくれる企業にこれまで出会ったことがなかった」と提案の可能性に大きな期待を寄せられました。
弊社では、同校がDXハイスクール校として掲げるキーワード「地域に生きるDX人材」に合わせ、地域課題の発見・解決ができる人材の育成を目指した「理数探究基礎」の年間カリキュラムを設計。また、年間の授業の内容については、各類型の特長を生かしつつ、卒業時の姿(グラデュエーション・ポリシー)と評価軸を紐付け、「探究で伸ばした力が、生徒一人ひとりの進学・就職のパスポートになる」よう配慮しました。


▲ ドローンのプログラミングをする様子


▲ ドローンの飛行前にチェックをする様子(写真 左)、飛行中のモニターチェックをする様子(右)
※ いずれの写真も昨年度、学校教育にドローンを活用できるかを実証した際に撮影されたものです。
整備したハードと学校の実態をうまく融合することが肝となる ― DXハイスクールの予算活用の要諦
津嘉山先生はDXハイスクールで文部科学省から得られる予算の配分について、「本事業の予算を生かし、整備したハードと学校の実態をうまく融合することで、より柔軟で実効性のある教育環境の構築が可能となる」と主張しています。また、ハードの整備を第一歩としながらも、①スクール・ポリシー(学校の教育目標)→②学習成果指標(育みたい力)→③探究カリキュラム(具体的な学び)の順に「逆算設計」することが、生徒の成長と学校改革を両立させる上で非常に重要だと続けられます。
弊社はこの思想を共有し、同校に次のステップを提示しています。
1.伴走3カ年計画 : 年度末ごとに成果を数値化し、翌年のプログラムを再設計
2.教員リーダー育成: モデル授業+共同研究で校内ファシリテータを養成
3.全国への横展開 : 成果指標と実践パッケージを公開し、全国の学校のDX推進を支援
弊社は同校との連携を、多様な資質・能力とその成長を可視化するアセスメントを提供できるからこそ可能な新たな学校支援の一つの形として、結実させようと考えています。特にDXハイスクールの予算の構造上、2年目以降は徐々に予算枠が減っていくこともあり、ハード購入費としては活用が難しくなっていくほか、事業成果に直結するカリキュラムの工夫や探究プログラムの磨き込みも重要になっていくはずです。
「DXハイスクールは挑戦の加速装置。遅かれ早かれ全国の学校でDX人材育成のための教育カリキュラムは進むはず。ヴィジョンをもって早く手を挙げた学校には生徒の学びと学校の在り方をアップデートするための予算と未知の学びがまっている」(津嘉山先生)
学校独自の特長を打ち出しつつ、「地域に生きるDX人材」の育成の達成と地域課題解決を同時に目指す沖縄県立本部高等学校の取り組みにぜひご注目ください。