【探究への道 第43回】梅北瑞輝先生 (宮崎県立飯野高等学校)

探究の設計と構築にフォーカスし、実際にカリキュラムをデザインされた先生方に実践をご紹介いただいています。
今回は、宮崎県立飯野高等学校(宮崎県)の梅北瑞輝先生にご担当いただきます。
.jpg?width=232&height=250&name=%E6%A2%85%E5%8C%97%E7%91%9E%E8%BC%9D%E5%85%88%E7%94%9F%20(%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E9%A3%AF%E9%87%8E%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1).jpg)
本校は、地域協働の探究を教育活動の柱に据える小規模校です。生徒は地域と自らの将来を探究する地域プロジェクトに取り組み、次世代を見据えた、地域の魅力創出および地域社会に貢献できる「未来を担うグローカル・ヒーロー」の育成を目指しています。本校の核となる探究の特長の一つとして、自由度の高い学びとキャリア教育にも通ずる実践が挙げられます。
探究活動を通して「問いを立て、主体的に行動する力」「多様な価値観を受け入れ、協働する力」「課題を発見し、解決策を実行する力」を育む中、生徒は地域社会と関わることでリアルな課題にも直面。その解決に向けた実践や未来志向の実践を積み重ねていきます。こうした経験を通して、自らのキャリアを見据えながら、社会に貢献できる人材へと成長することを願っています。また、学校・地域が一体となって、生徒の「心が揺れる瞬間」を作ろうと奮闘しています。
また、探究活動では「生徒が自走する」ことも重視しています。プロジェクトの自由度を高めることで、生徒個人の興味・関心に基づく学びを促し、自ら考え行動する力を養います。また、地域をはじめ県内外の専門家や企業、国内外の大学とも連携。実社会とつながったプロジェクトを展開することで、学びの実感を高めています。さらに、探究とキャリア教育を結び付け、進路選択の際に大切な探究の過程も重視しており、「ワクワク感」も大切にしながら学びを深めています。

▲ 空き家リノベーションプロジェクトの様子

▲ 地域事業者と地産地消の商品開発プロジェクトの様子
本校では、進路指導部がこうした探究活動とキャリア教育を担っています。両者を一体化させることで、生徒の自己実現にもつなげていくことを目指しているからです。例えば、「地域医療を考える高校生の会」を立ち上げた生徒は、地域事業者でつくる「地域医療を考える会」と協働してチーム医療に必要な医療関係者(医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚療法士、管理栄養士など)を集め、地域医療についてともに考える対話の会を設けました。これには、参加された医療関係者の方々の方が刺激を受けられたようで、高校生の実践としてメディアにも大きく取り上げられました。また経験を通して、企画立案や実施計画・運営、波及効果などの実践的なスキルを習得し「自らの手で地域を変える」という自信を得たものとなりました。プロジェクトのリーダーを務めた生徒は現在、国立大学の医学部(本校史上2例目の医学部進学者)で学んでいます。この他にも、年間を通して多彩なプロジェクトを実施しており、学びを求める生徒たちが県外や海外の研修プログラムへ越境していくようになりました。その数は全校生徒の1/4に当たる約50名にのぼります。

▲ 世界越境プロジェクト in マダガスカルの様子
こうした探究活動は、教員が一方的に指導するのではなく、伴走者として関わり、生徒の主体性をより引き出すことが重要です。加えて、探究活動の成果を発表する場は、小・中学生や地域の方々を招きプレゼンテーションの場を設けることで、実社会での発信力を養いながら、自らのフィードバック、プロジェクトの評価をもらうことなど、生徒の「心が揺れる瞬間」を創出し、学びの設計を進めています。
探究活動は、設計されたカリキュラムをそのまま実行してもうまくいきません。生徒が「ワクワクする仕組みづくり」や「いかに主体的に動くか」が重要だからです。そのためには、自由度の高いプロジェクト実践と、実社会(思いをもって実践している大人、ワクワクする人)とつながる学びの場を提供することが重要です。今年度は全校生徒約200名の本校が、学生数約7,000名の海外大学と連携協定を結び、学生が相互に学び合う環境も作りました。それはなぜか。教員が指導者ではなく伴走者として関わり、生徒の問いや挑戦を尊重する環境をつくることで、多くの生徒たちが自走し始めるからです。さらにキャリア教育の視点を加えると、生徒の将来を見据えた学びが実現できる。本校生の取り組みからそのようなことを日々感じています。
宮崎県立飯野高等学校
https://iino-hs.ed.jp/
文部科学省「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(地域魅力型)」報告
https://iino-hs.ed.jp/report

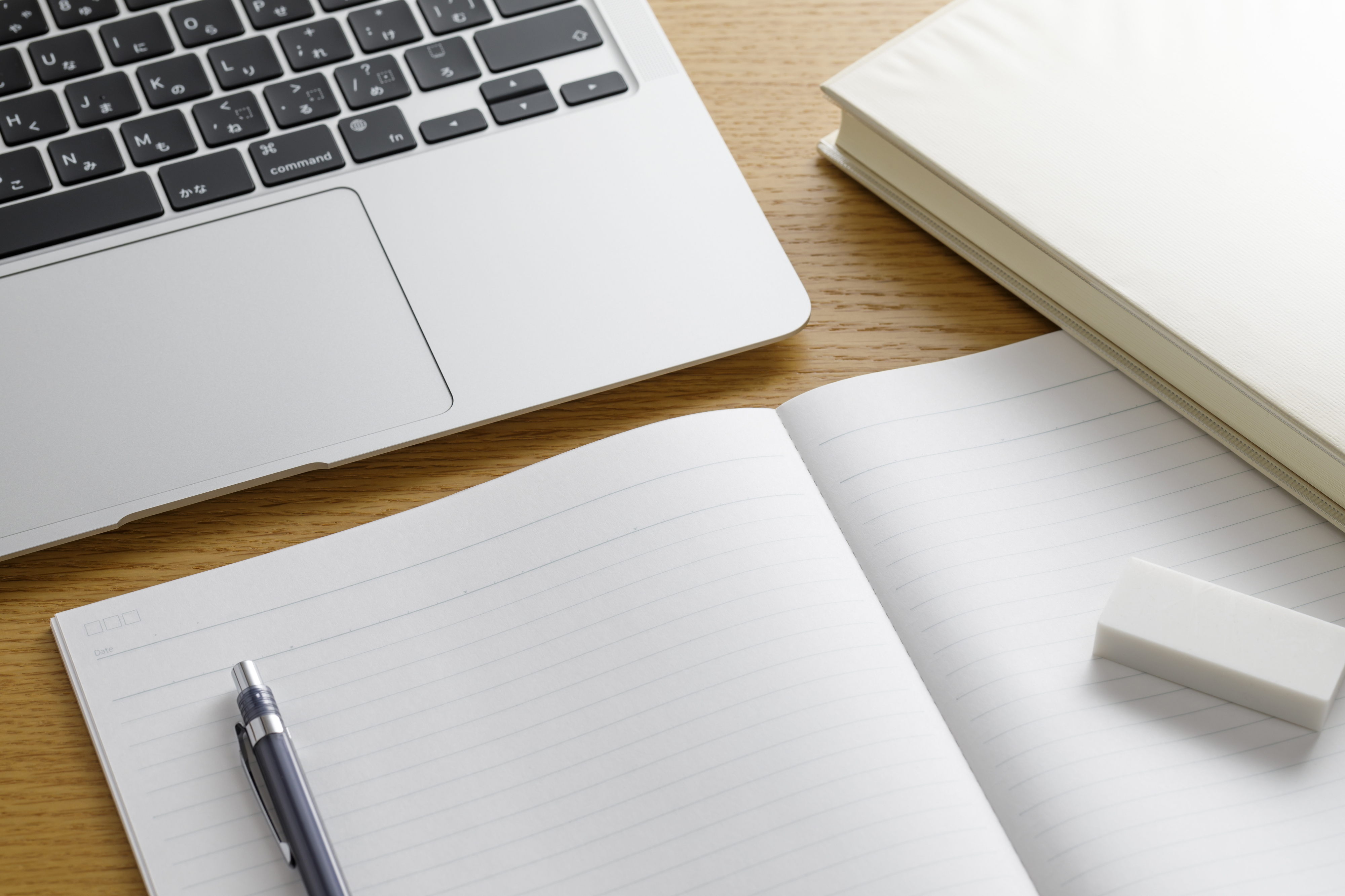
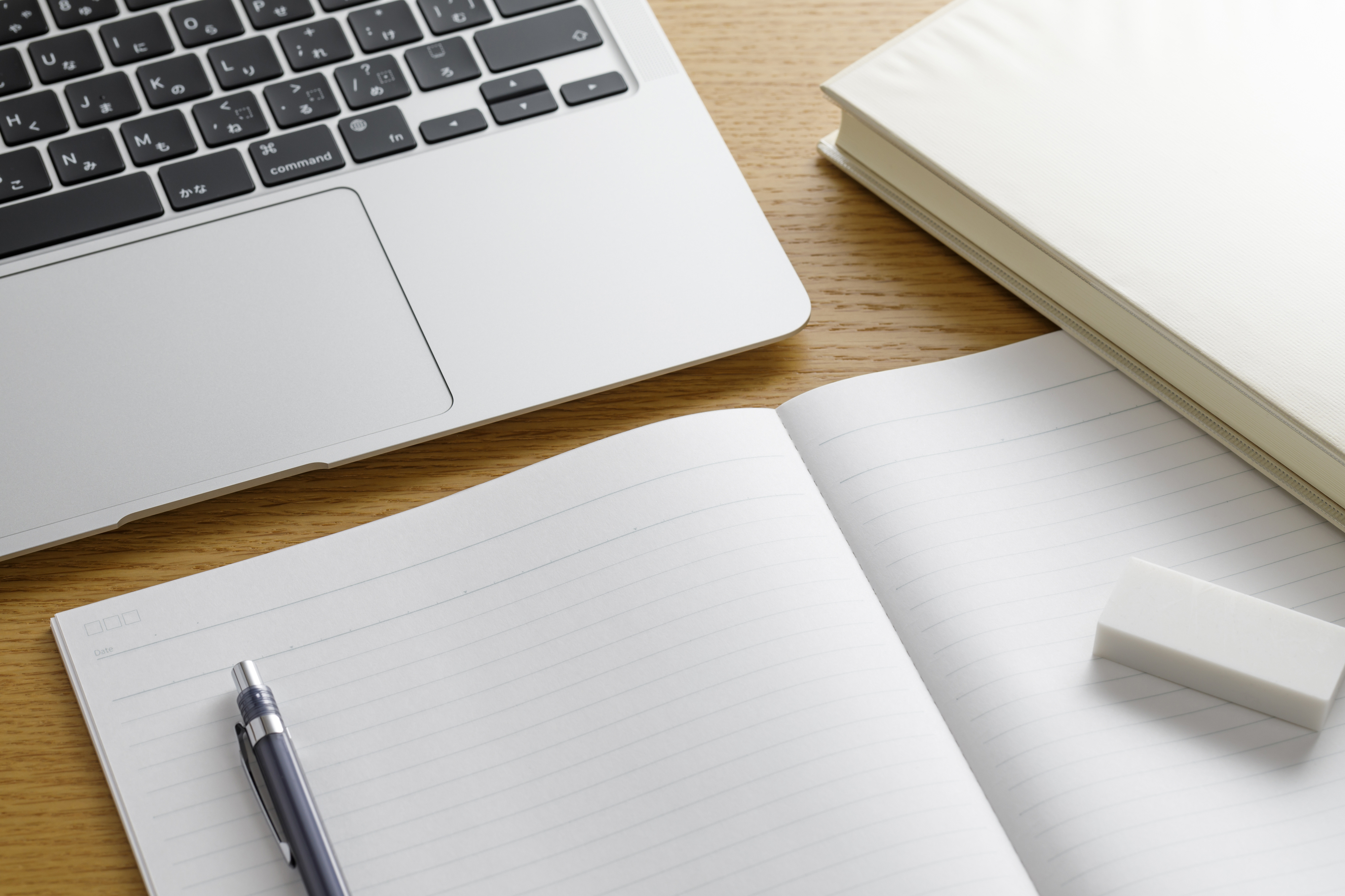
-1.jpg)